学校特集
関東学院中学校高等学校2025
掲載日:2025年7月1日(火)
緑豊かな横浜・三春台の高台にキャンパスを構える関東学院。『人になれ 奉仕せよ』をスクールモットーとし、キリスト教の普遍的価値を土台に、生徒が個性を発揮できる、のびやかな校風を育んできました。時代に即して柔軟に変化しながら、100年をこえる歴史を重ねてきた同校が、「生まれ変わる」と宣言して今、取り組んでいるのが、『入試』『カリキュラム』『選抜クラス』による『進路指導』を柱とした教育改革です。生徒の可能性をこれまで以上に引き出し、一人ひとりに合った進路選択を実現する、そのメソッドを、進路指導部の中村悠人先生(数学科)に伺いました。
『自走』と『共走』がテーマ
中村先生が2023年度に赴任して、同校の進路指導が大きく変わりました。生徒主体の進路実現に向け、取り組み方から鍛えていく、人づくりプロジェクトが着々と進行しています。

中村先生:進路指導における成果向上の条件として、『自走』と『共走』をテーマに掲げています。近年、進学実績を飛躍的に伸ばしている横浜翠嵐高校に近いイメージで指導しています。例えば、数学の授業も、『共走』(学び合い)をテーマに行っています。イメージとしては共有学習です。個別に問題を解いた後、解き方をみんなで共有し、検討します。『共走』すると、周りに刺激を受け、学力をぐんぐんと伸ばすきっかけになります。
そのイメージを、中村先生は『炭』に例えて、わかりやすく生徒に伝えています。
中村先生:炭は、1本だとそれほど強い火力ではありませんが、たくさん集まるとバーベキューができます。その炭をキャラクター化して、『みはるたん』と名づけています。この『みはるたん』1本1本が関東学院生です。「みはるたんが、もっともっと燃え上がるように共走しよう」と日頃から伝えています。
中村先生が高1から受け持つ学年は、今春高3になったばかりですが、「模試の結果を見ると、文系も理系も一皮むけてきた感じがする」と話します。
中村先生:進路指導において大事なことは、授業と進路指導を掛け算することです。つまり、教員側が二刀流の姿勢で指導する意識を持たなければいけません。
その考え方を先生方にも意識してもらう目的も兼ね、礼拝堂に全員集めて行う『進路集会』(ガイダンス)を、年に7、8回、実施しています。合間に、難関国立10大学や早稲田大学、慶應義塾大学志望者を対象とした『最難関大ガイダンス』をはじめ、国立大学志望者向け、東京大学志望者向けと、同じ志望の生徒を集めた『進路集会』も、実施しています。
中村先生:進路集会は『みはるたん』に火をつける、良い機会になります。『進路集会』の後に一度モチベーションが上がるので、効果的に実施しています。主に進路担当者が話をしますが、他の先生方も生徒もともに聞いているので、学年の中でベクトルがズレることなく、学年全体で対応することができています。
伸長の必要十分条件は『自己開発』
指導のピークは、高2の12月に行う『第一志望宣言』になります。
中村先生:生徒が第一志望の大学、志望理由、試験科目を書き、保護者の方からも一筆いただいて、提出します。それを担任、進路指導主任、学年主任、校長が目を通して、印鑑が押された状態で返ってきます。これで生徒は覚悟を決めるわけです。国公立大学後期も含めると、約1年と3ヶ月。再びスイッチを入れて頑張っていくという流れに持っていきます。
2025年度高校3年生は国公立大学志望者が約70名。そこに早稲田大学、慶應義塾大学などの志望者を加えて、いわゆる難関と呼ばれる大学を100名程度が志望しています。学年に約230名の生徒が在籍しているので、半数近くが最上位を目標としています。
この火力を維持するために、同校は『自走』にも力を入れています。
中村先生:そもそも『みはるたん』に火がつかなければ、『共走』は始まりません。本校では『知層』という学習時間調査を実施しています。イメージはまさに地理の『地層』です。13万年前にできた地層が、今の三春台の土台であるように、低学年でのスタディライフバランスが関東学院生の将来の土台となる、という考えのもと、学習時間(教科別)、部活、遊び、それぞれの時間を塗って、毎日の状況を可視化するシートを配布しています。
最近、携帯のスクリーンタイム(携帯を何時間見ているか)も追加しました。2週間、記録したら、振り返りを記入して提出します。振り返りを書ける人のほうが、書かない人よりも1.23倍、生産性が高くなるという研究結果も出ているので、振り返りまできちんと書くように指導しています。『知層』は中学生にも導入しており、中学から始めた生徒たちが、6年後にどのような進路実現をするのか、結果が楽しみです。
毎日の過ごし方を記録する目的は、教員が生徒を管理するためではありません。生徒が自分を管理する能力を身につけるためです。
中村先生:高校生に学習時間は平日3時間・休日5時間。長期休業中は8時間、睡眠時間は8時間、「そうすれば8時間も遊べるでしょ」という話をして、生活リズムを意識させるようにしています。モチベーションに頼らない「やるべきときにやるべきことをやる」という意識を育てる意味で学習習慣の形成に努めています。
中村先生が同校に赴任した当初は「学習の取り組みに甘さがある」生徒たちでしたが、高3の今、担任をしている高3理系の『選抜クラス』だけでなく、『一般クラス』も含めて、「休日は4時間ぐらい勉強するようになっている」と言います。
中村先生:部活動と勉強は≒(ニアリーイコール)なんです。どちらの活動も、目的は『自己開発』です。ですから、生徒には「昨日の自分より今日の自分がよくなり、明日の自分が今日の自分よりも更によくなるために、今、何をするべきなのかを考えて生活してほしい」と話しています。
スランプに陥るなど、迷走する生徒たちは、「勉強時間が取れなかった」とか、「昨日の自分が許せない」とか、そんなことを言い始めるものですが、生きていく上では、次の1時間1分1秒をどう過ごすのかを考え、生産性を高めていくことが大事なんです。伸長の必要十分条件は『自己開発』だと考えています。
早くから意識を高めるために、本校では『選抜クラス』を中2から設けています。中学入試の結果で選抜クラスのメンバーを決めてしまうことがありがちですが、そうではありません。中学生は成長速度に幅があるので、ゆっくり成熟していく生徒も十分に伸ばすことができる仕組みとなっています。
逆に早熟で、入学後に伸び悩む生徒もいます。毎年、クラスの入れ替えを行いますので、自分の学力に合うクラスで授業を受ける。そこで学校生活を送ることにより、立て直しができ、再び伸びていくケースも多々あります。
ダイバーシティの時代にふさわしく、それぞれが自分の目標を持ち、その目標に向かって自己開発をどう展開していくのか。それを考えていくのが本校の進路指導になります。
私は、本校のスクールモットー「人になれ 奉仕せよ」も自己開発だと思っています。自分を開発できない者が、人に奉仕しても意味がないと思うからです。自らが向上して、周りにも供給できるようなサーバントリーダーを目指すことが、この学校のスタイルだと考えています。
数学は習熟度別授業も織り交ぜて効率アップ

『共走』をテーマに行われている数学の授業を深掘りすると、例えば、理系の数学の授業は『発展クラス』と『標準クラス』に分けて実施。高校3年の5月までに数学Ⅲの学習を修め、総合演習に取り組めるよう、速習を目指しています。
中村先生:教材は、書き込み式のプリントで、あらかじめ穴を開けているので、ルーズリーフバインダーだけ用意してもらい、そこにまとめて保管するように伝えています。
授業では、プロジェクターでプリントを投映し、要点を解説していきます。読めばわかることは板書しません。投影するのは、解説の時短を図り、生徒が自ら手と脳を動かす時間を増やすためです。
生徒たちはYouTube慣れしているので、ゆっくりした授業展開は飽きてしまうことが多いです。1.2倍速ぐらいで動けるように準備して、授業に臨みます。
もちろん、中には数学に苦手意識をもっている生徒もいます。その場合は、授業後に手厚くフォローします。
中村先生:習熟度別授業が理想的と考え、現在、理系数学の授業は習熟度別(発展クラス・標準クラス)で行っています。高校3年の5月までに数学Ⅲの学習を修め、総合演習に取り組めるよう、速習を目指しています。
同校では授業教材以外にも副教材を持たせています。授業担当者で使い方は様々ですが、中村先生は月に1回実施するテストの範囲としています。
中村先生:高2の4月はここ、というように試験範囲が決まっていて、その中の類似問題を出題します。基本的に大学入試問題ばかりです。高2から月に1度、テストを行い、入試レベルまで塗り重ねていきます。
1問1問、進捗【×:誤答、△:発想は出た、□:立式できた、(発想・立式ができた上での)◯=計算ミス、◎=完答】を記入する『精練カード』を配布し、テストの点数のうちの10点分が、カード提出点になります。
中村先生:テストで思い通りの点数が取れなかったとしても、頑張って真面目に勉強してきた生徒は、その分、点数が取れる仕組みになっています。また、こちらはその分難しい問題を出すことができます。共通テスト対策の教材もカードで点数を報告させ、提出点に入れています。
生徒たちにしてみると忙しいのですが、模試や共通テスト本番時には、一律に、ある程度の問題量をこなして受けられている状態になるような仕組みを作るようにしています。進路実現には、かなりの学習進度が必要になります。それを保証してあげないと、進路実現は難しいので、その点を意識して授業をするようにしています。
自己満足できた状態で卒業してほしい
中村先生が、同校に赴任して2年。学内の雰囲気をどのように感じているのでしょうか。
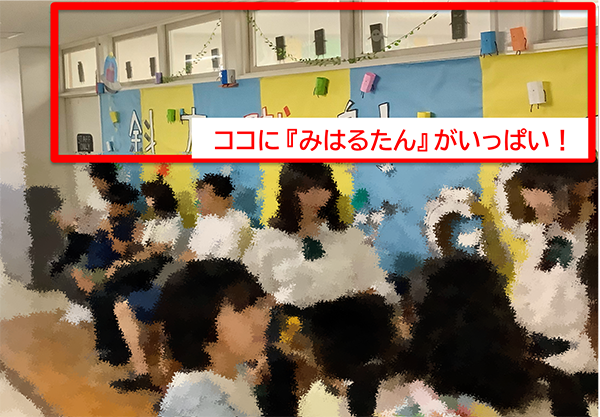
中村先生:本校の生徒たちはたいへんやる気があります。こちらが声を掛けると、ノリよく「もっと上に行ってやろうぜ」といった雰囲気になるので、何事にも明るく挑戦できます。そういうところが、本校の文化だと思います。『みはるたん』をキャラクターにして、文化祭で出し物をやるようなノリの良さもあります。
ですから、先ほどの『知層』シートを、ホームルームの時間に投映して、「頑張ってるね」とか「もうちょっと頑張らないといけないよね」などコメントしながら、共有します。クラスの中に、こんなにしっかりやっている人がいるんだ、ということがわかると、何らかの刺激を受けますよね。(知層シートを)見られるから頑張る、という生徒もいます。
また、『解説動画』を自作して、YouTubeに限定公開で配信しています。漫画家さんが仕事をするような液晶タブレットに、タッチペンで書き込みながら、解説します。
『解説動画』は、生徒が自走する手助けになればと思い始めました。生徒にも好評です。
中村先生:授業で聴き慣れた言い回しで説明されると、頭に馴染みやすいですよね。
【1から(n-1)までのK分の1、-(K+1)分の1、......青ペンに持ち替えます。これをやっていくと、1分の1-2分の1、これはK=1を代入した時です。2を代入すると2分の1、-3分の1です。ずっと行って、最後は(n-1)を代入するので、n-1分の1、-n分の1となります】みたいな感じで......。ただし顔は出しません。
重要単元の、網羅性の高い解説をストックしているので、生徒は自分のタイミングで、ほしい解説を取り出せます。まず自分でやってみて、わからなければ翌日、質問に来ます。
『解説動画』の原点は、コロナ禍でした。
中村先生:そのときは前任校の横浜翠嵐で教鞭をとっていましたが、休校中の授業はオンラインではなく、オンデマンドでした。先生全員が『解説動画』を使いこなすと、生徒があっという間に速習を終え、進学実績が跳ね上がりました。そのときの手応えが、今、本校でも役に立っています。
教材の中にQRコードを埋め込みます。そのQRコードをその場で読ませて、授業中の振り返りで使ったり、ほしい動画を探す手間を省く工夫をしています。
最後に中村先生に目指すところを伺うと「お互いに自己開発して、お互いに自己満足できた状態で、巣立ってもらうことが理想」という答えが返ってきました。
中村先生:毎年、生徒が変われば、担当している先生方も変わります。進路指導部には10名ほどの先生がいて、リーダーは私よりも若いのですが、方針をきちんと出してくれています。その方針に沿って、各学年で具体的な進路指導をしていくことに加え、進路指導部の教員が毎年、1人1つ企画を立案し、体験学習プログラムも実施しています。昨年、私は東京大学大学院博士課程に在籍する卒業生の研究室に、約50名の生徒を連れて行きました。各先生がいろいろなプログラムを開拓しているので、そういうことも取り入れながら、生徒と教員がお互いに自己開発して、お互いに自己満足できた状態で卒業を迎えられればいいなと思っています。
進学校で培った経験を生かして、関東学院の校風や、生徒に合う形でアレンジしながら、生徒一人ひとりが満足する進学選択ができるよう、導いている中村先生。『進路指導』を柱とした教育改革の騎手として、エネルギッシュに生徒と向き合っています。その熱量を、ぜひ三春台のキャンパスを訪れて感じてください。


